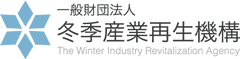SAVE THE SNOW
カラーに込めた想い
2030年までに世界中で達成すべき17の社会課題に対し、冬季産業観点からも達成に貢献するという意思を込めました。"雪の降る地球" を実現するとともに "雪と共存する人類" がより幸せな生活を送れるよう、活動を行っていきたいと考えています。(雪山から貧困を考える。スノースポーツで生涯健康に貢献する。スキー学校でジェンダー課題や教育課題に貢献するなど…)17の課題の中で、特に注力すべき7項目の色で雪の結晶を彩りました。

上記7つのカラーを雪の降るために必要な『太陽』『水』『緑』にたとえ、SEVEN SNOW COLORSとして、SNOWの『O』を表現しています。そして、その他10項目の色も「SAVE THE SNOW」の文字の色として使用しています。
お知らせ
- 2024年3月26日:
SAVE THE SNOW Concert 開催いたしました。 - 2024年1月23日:
NHK「ニュースウオッチ9」放送のお知らせ - 2024年1月5日:
【総合演出:松任谷正隆、出演:松任谷由実、平原綾香】SAVE THE SNOW Concertの開催について - 2023年10月27日:
三井不動産×冬季産業再生機構×JOCで連携「三井不動産グループの“終わらない森”創り」で地球の環境保全に貢献 - 2023年6月5日:
カスタムフェア(東京会場)SAVE THE SNOW ブース出展のお知らせ - 2023年6月2日:
公式LINEのオープンのお知らせ
設立への想い
1. 冬季産業の発展と現状
日本のスキー発祥は、1911年1月12日、当時の高田(現上越市)に滞在していたレルヒ少佐が、スキーの滑走方法を指導したことが始まりとされています。日中戦争の影響などで1940年に札幌での開催を予定していた冬季五輪は幻となりましたが、1972年に日本・アジア初の冬季五輪として、満を持して札幌大会が開催されたのを機に、日本における冬季産業は、競技スポーツとして普及して参りました。1980年代~90年代前半には、レジャーとしてスキーを楽しむ人も増えました。1987年に制定された総合保養地域整備法(リゾート法)やバブル景気により、日本全国でスキー場やリゾート施設の建設に拍車がかかり、700箇所以上のスキー場が作られました。また、同時期である1987年に映画『私をスキーに連れてって』が公開されたこと等をきっかけにスキーブームが起こり、スキー人口は1860万人に達し、冬季産業は最高潮へ達しました。1998年には長野において日本で二度目となる冬季オリンピックが開催され、産業として成熟期を迎えましたが、その後のバブルの崩壊やレジャーの多様化、若年層のスキー離れなどの影響により、スキー人口は約20年間でピーク時の3分の1程の700万人まで落ち込みました。
2.「雪資源」としての新たな可能性
近年、訪日外国人により我が国の『雪資源』が注目されるようになりました。また、2017年以降は右肩上がりでスキー・スノーボード人口が増加傾向となっており、国内需要からも新たな可能性として冬季産業が見直されて来ています。冬季産業再生機構では冬季産業が昭和~平成で培った現状を検証し、地域活性化や観光業さらには交通インフラ整備等、社会・経済全体の発展の一助となるよう努めるとともに、冬季産業に関わる人材の育成・教育を行うことにより、国内そして世界へ我が国の誇る『雪資源』の価値を広めて参る所存です。
3. 環境問題への取り組みと冬季産業の活性化への貢献を目指して
冬季産業再生機構は環境問題を最も注力すべき課題と捉えています。地球温暖化による『雪資源』への影響は冬季産業にとって先送りできない問題だからです。経済活動を進める中で冬季産業では多くの森林伐採を行ってきました。リゾート法の改正で700箇所以上に膨らんだスキー場も、現在は半数が稼働していないにもかかわらず、コースは国有林含め植樹・植林されず手付かずの状態です。冬季産業再生機構は、SDGs17項目のうち主に7項目を取り組むべき課題と捉え、豊かな地球環境と日本保有財産である『雪資源』を保全しながら経済活動の活性化に貢献して参ります。
一般財団法人冬季産業再生機構
代表理事 / 会長 皆川 賢太郎
代表理事 / 会長 皆川 賢太郎
事業目的
一般財団法人冬季産業再生機構は、雪を資源と捉え、刻々と変化する地球環境に配慮するとともに、地球温暖化や海洋汚染、また森林破壊や大気汚染といった環境破壊がもたらす影響の調査・研究、及び問題解決に向けて持続可能な取り組みを推進し、循環型社会の実現に寄与することを目的として設立致しました。活動の中心事業として、"SAVE THE SNOW" を主催し、プロジェクトベースでSDGsにおける各種課題と向き合いながら、雪資源を守るための様々な活動を行なって参ります。事業内容
(1)地球温暖化、森林伐採等の環境問題に関する調査・研究(2)植林、植樹等緑化に関する調査・研究
(3)訪日外国人に関する調査・研究並びに観光先進国実現に向けた戦略立案
(4)まちづくり事業、地域活性化事業、環境計画等に関する調査研究及びこれらの戦略立案
(5)国有地、雪資源等の資源活用方法の調査・研究
(6)冬季産業に関する調査・研究並びに冬季産業の再生・活性化に向けた戦略立案
(7)冬季産業に関する人材の育成・指導
(8)冬季産業に纏わる再生エネルギーについての調査・研究
(9)前各号に関するイベントの企画、運営、広告、宣伝、広報、出版物の制作及び販売
(10)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
※事業は、日本国内において行うものとする。
組織
理事・監事

代表理事 / 会長
皆川 賢太郎〔Kentaro Minagawa〕

代表理事 / 会長
皆川 賢太郎〔Kentaro Minagawa〕
- 元アルペンスキー日本代表
- 株式会社HEIDI 代表取締役社長
- 株式会社岩手ホテルアンドリゾート 顧問 兼Resort事業統括本部 統括
- 公益財団法人日本オリンピック委員会 選手強化中長期戦略プロジェクト サービスマネージャー 兼 データ&テクノロジーWG リーダー
- 一般社団法人日本アーバンスポーツ支援協議会 理事
- 公益財団法人コーセー小林スポーツ財団 理事
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター アンバサダー
1998年 長野オリンピック
2002年 ソルトレークシティオリンピック
2006年 トリノオリンピック
2010年 バンクーバーオリンピック
4大会連続日本代表として出場
CLOSE
2002年 ソルトレークシティオリンピック
2006年 トリノオリンピック
2010年 バンクーバーオリンピック
4大会連続日本代表として出場

専務理事
青井 茂〔Shigeru Aoi〕

専務理事
青井 茂〔Shigeru Aoi〕
- 株式会社アトム 代表取締役社長
- 株式会社TOYAMATO 代表取締役
- コートヤードHIROO オーナー
カリフォルニア州サンタクルーズのO'neill社にて、創業者のジャック・オニールが組成したSea OdysseyProgramに従事。帰国後、デロイト・トーマツ・コンサルティングにて会計業務を基礎とした大企業の分社化や特殊法人の民営化プロジェクト等を担当。その後、産業再生機構にて企業の再生案件に従事。日本国内の各所にある事業所にて、各企業の従業員と共に働き、そのなかの会話を通じて、再生に向けての課題を顕在化させ、企業の経営陣と共にPDCAを実施した。2011年に代表取締役副社長、2019年代表取締役社長に就任。
CLOSE

理事
太田 雄貴〔Yuki Ota〕

理事
太田 雄貴〔Yuki Ota〕
- 国際フェンシング連盟 副会長
- 一般財団法人日本アーバンスポーツ支援協議会 副会長
- 一般社団法人日本eスポーツ連合 特別顧問
- 公益財団法人日本オリンピック委員会 オリンピック・ムーブメント専門部会 副部長
- 公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構 アスリート委員会 委員
- 一般社団法人日本ハンドボールリーグ 理事
- WIN3株式会社 代表取締役
- 株式会社マイネット 社外取締役
- 元公益社団法人日本フェンシング協会 会長
2004年 アテネオリンピック9位
2008年 北京オリンピック銀メダル
2012年 ロンドンオリンピック銀メダル(フルーレ団体)
2015年 世界選手権金メダル獲得
CLOSE
2008年 北京オリンピック銀メダル
2012年 ロンドンオリンピック銀メダル(フルーレ団体)
2015年 世界選手権金メダル獲得

理事
堤 正利〔Masatoshi Tsutsumi〕
評議員

評議員
北野 貴裕〔Takahiro Kitano〕

評議員
北野 貴裕〔Takahiro Kitano〕
- 北野建設株式会社 代表取締役会長兼社長
- Sakura Hanoi Plaza Investment Co., Ltd. MANAGING DIRECTOR
- 川中嶋土地開発株式会社 代表取締役社長
- 株式会社アサヒエージェンシー 代表取締役会長
- 株式会社長野放送 取締役相談役
- 株式会社キタノプロパティ 代表取締役社長
- 株式会社ライフプラス代表取締役会長
- 一般社団法人日本スノースポーツ&リゾーツ協議会 会長
- 公益財団法人大崎企業スポーツ事業研究助成財団 理事
- 一般社団法人長野県建設業協会 理事
- 一般社団法人日本建設業連合会 理事
- 公益財団法人日本ボブスレー・リージュ・スケルトン連盟 代表理事会長
- 一般社団法人太平洋協会 代表理事会長
- 在東京ソロモン諸島名誉領事館 名誉領事
- 公益財団法人日本オリンピック委員会 評議員
- 公益財団法人長野県スキー連盟 会長
- 元公益財団法人全日本スキー連盟 会長
1963年10月6日生まれ
平成3年北野建設株式会社社長室長に就任。平成4年同取締役に就任。平成6年同常務取締役に就任。平成10年同専務取締役に就任。平成15年同代表取締役副社長に就任。平成19年同代表取締役会長兼社長 執行役員社長に就任。様々な競技の普及振興に寄与している。
CLOSE
平成3年北野建設株式会社社長室長に就任。平成4年同取締役に就任。平成6年同常務取締役に就任。平成10年同専務取締役に就任。平成15年同代表取締役副社長に就任。平成19年同代表取締役会長兼社長 執行役員社長に就任。様々な競技の普及振興に寄与している。

評議員
中島 周〔Amane Nakashima〕
アンバサダー

アンバサダー
元フリースタイルスキー・モーグル
日本代表
元フリースタイルスキー・モーグル
日本代表
上村 愛子〔Aiko Uemura〕

アンバサダー
元フリースタイルスキー・モーグル日本代表
元フリースタイルスキー・モーグル日本代表
上村 愛子〔Aiko Uemura〕
- ワールドカップ モーグル(優勝9回、2位8回、3位10回)/デュアルモーグル(優勝1回、2位5回、3位1回)
- ワールドカップ 2008年 種目別年間優勝(日本モーグル史上初)
- 世界選手権 モーグル(優勝1回、3位1回、入賞2回)/デュアルモーグル(優勝1回、3位1回、入賞2回)
- 1998年 長野オリンピック 7位入賞
- 2002年 ソルトレイクシティオリンピック 6位入賞
- 2006年 トリノオリンピック 5位入賞
- 2010年 バンクーバーオリンピック 4位入賞
- 2014年 ソチオリンピック 4位入賞
アルペンスキーからモーグルに転向して4年、初出場した長野五輪で一躍注目を集め、日本のエースとして常にメダルを期待される存在となる。世界トップ選手のひとりとして、日本勢の成績を数々塗り替えた。ワールドカップ種目別年間優勝、世界選手権優勝を果たし、「No.1」の称号を手に入れる。残る五輪のタイトルを賭けて通算5回出場ですべて入賞を果たすも、悲願を達成することは叶わなかった。3Dエア(コークスクリュー720)を最初に完成させ、カービングターンを武器とするなど、世界の女子モーグ
ル界における技術の先駆者としても知られる。現在はスキーフリースタイル普及のため次世代の選手育成にも力を注いでいる。
CLOSE

アンバサダー
プロスキーヤー(フリースタイルスキー)
プロスキーヤー(フリースタイルスキー)
小野塚 彩那〔Ayana Onozuka〕

アンバサダー
プロスキーヤー(フリースタイルスキー)
プロスキーヤー(フリースタイルスキー)
小野塚 彩那〔Ayana Onozuka〕
2歳からスキーを始める。アルペンスキー、スキー技術選ともにトップ選手として活躍していたが、スキーのハーフパイプが2014年ソチオリンピックで正式種目となるタイミングで競技転向を決意。転向後はアメリカをベースにワールドカップ(以下、W杯)を転戦。2年目にはW杯年間総合ランキング3位、世界選手権3位、W杯最高位2位をマークした。この種目で日本人女性初となるエクストリーム系スポーツの最高峰X-GAMESのインビテーションを獲得。
着々と実績を積み、トップ選手の仲間入りを果たすと、2014年、初めて出場したソチオリンピックでは銅メダルを獲得。
2014-15、2015-16の2シーズン続けてW杯の年間総合優勝を達成。2017年の世界選手権では金メダルを獲得し、世界の頂点を極めた。2大会連続出場となった平昌オリンピック(2018年)は5位入賞。 現在はフリーライドスキーに転向。日本人女性として初めてFreeride World Tourのワイルドカードを取得した。
CLOSE
着々と実績を積み、トップ選手の仲間入りを果たすと、2014年、初めて出場したソチオリンピックでは銅メダルを獲得。
2014-15、2015-16の2シーズン続けてW杯の年間総合優勝を達成。2017年の世界選手権では金メダルを獲得し、世界の頂点を極めた。2大会連続出場となった平昌オリンピック(2018年)は5位入賞。 現在はフリーライドスキーに転向。日本人女性として初めてFreeride World Tourのワイルドカードを取得した。

アンバサダー
プロスノーボーダー
(スロープスタイル/ビッグエア)
プロスノーボーダー
(スロープスタイル/ビッグエア)
鬼塚 雅〔Miyabi Onitsuka〕

アンバサダー
プロスノーボーダー(スロープスタイル/ビッグエア)
プロスノーボーダー(スロープスタイル/ビッグエア)
鬼塚 雅〔Miyabi Onitsuka〕
5歳のときに福岡市の室内練習場ではじめてスノーボードを始めた鬼塚雅(おにつか・みやび)。小学校1年生のときに初出場した国内大会にて見事初優勝し、天才スノーボード少女と謳われ、7歳のときにはバートンがスポンサーとなる。2013年には『サウスアメリカンカップ』で優勝。2014年の全日本選手権では圧巻の滑りで優勝を成し遂げる。2015年1月、『スノーボード世界選手権』女子スロープスタイルに日本代表として出場。決勝でキャブ900をメイクするなど完璧な滑りをみせ、92.50点の高得点を叩き出し、男女を通じて『スノーボード世界選手権大会』史上最年少(16歳3ヶ月)での優勝を成し遂げた。世界が注目する日本女子スノーボード・スロープスタイルのエースボーダーである。また、2020年1月には『X Games Aspen』にてビッグエアー部門で初優勝を飾る。大学在学中の2018年に平昌オリンピックに出場。2022年、北京オリンピックの女子スノーボード・スロープスタイルとビッグエアに出場。
CLOSE

アンバサダー
プロスキーヤー
(デモンストレーター)
プロスキーヤー
(デモンストレーター)
栗山 未来〔Miku Kuriyama〕

アンバサダー
プロスキーヤー(デモンストレーター)
プロスキーヤー(デモンストレーター)
栗山 未来〔Yoshiki Takahara〕
- 2017年 全日本スキー技術選 女子総合1位
- 2018年 全日本スキー技術選 女子総合1位
- 2019年 全日本スキー技術選 女子総合1位
- 2021年 全日本スキー技術選 女子総合7位
- 2012年 全日本スキー技術選 女子総合1位
- 2013年 全日本スキー技術選 女子総合6位
- 2017年 IVSIスノースポーツ国際会議
- 2023年 INTERSKI世界スキー指導者会議
- SAJSNOWAWARD 優秀選手賞4回受賞
- 全日本スキー連盟ナショナルデモンストレーター5期
985年11月9日生まれ 富山県出身
GALA湯沢スキークラブ所属
スキー好きの両親に連れられ3歳からスキーを始め、10歳からはたくさんスキーができるとの思いから、アルペンスキーに打ち込み、インターハイ・国体に出場。
その後、基礎スキーに転向。小柄ながらスピードのある中でも大きく歯切れの良い滑りを武器に、スキー技術選手権大会4回優勝。
また、スキーを通じて得た体験や学びを多くのスキーヤーに伝え、幅広い年齢層で楽しめるスキーの普及活動を行う。
CLOSE
GALA湯沢スキークラブ所属
スキー好きの両親に連れられ3歳からスキーを始め、10歳からはたくさんスキーができるとの思いから、アルペンスキーに打ち込み、インターハイ・国体に出場。
その後、基礎スキーに転向。小柄ながらスピードのある中でも大きく歯切れの良い滑りを武器に、スキー技術選手権大会4回優勝。
また、スキーを通じて得た体験や学びを多くのスキーヤーに伝え、幅広い年齢層で楽しめるスキーの普及活動を行う。

アンバサダー
プロスキーヤー
(アルペン/ビッグマウンテンスキー)
プロスキーヤー
(アルペン/ビッグマウンテンスキー)
佐々木 明〔Akira Sasaki〕

アンバサダー
プロスキーヤー(アルペン/ビッグマウンテンスキー)
プロスキーヤー(アルペン/ビッグマウンテンスキー)
佐々木 明〔Akira Sasaki〕
1981年生まれ。
中学1年のとき、生まれ育った北海道の小さな町の書店で出会った1枚の写真。それは70年代にスケートボードの一大ムーブメントを巻き起こしたカリフォルニアの映画『DOGTOWN & Z-BOYS』のカバー。佐々木は、既成概念にとらわれないスケートボードのワンショットに強く惹かれ、自身のスキーに取り込もうと考え始めた。
アルペンレーサーとして頭角を現し、19歳で世界選手権とワールドカップデビュー、21歳でソルトレイクオリンピック、その後、トリノ、バンクーバー、ソチと4大会連続オリンピック出場。ワールドカップでは3度の2位表彰台(アジア人最高位最多)という輝かしい記録を残している佐々木。
幼少期からレース一筋でストイックに練習を繰り返す選手が多いアルペン界において、現役時代もハーフパイプで飛んだり、パウダーも楽しむフリースタイルな要素を持ち合わせる佐々木は異色な存在だ。その根底には、カウンターカルチャーへの憧れと、ジャンルを固定しない少年時代の自由なスキー環境が影響している。世界で勝つためにはこうあらねばならない、というスキー界の古典的な秩序に静かに反発し、結果を出すことで自分のスタイルを貫く。特に65番スタートからトップ争いに食い込んだ2002年ウェンゲンWCでの表彰台は、世界でも大きな話題となり、欧州にファンクラブが結成されたほどだ。
15年に渡り第一線で活躍した佐々木は、東日本大震災でのボランティア活動での出会いをきっかけに、アルペンレースというスキーのカテゴリーに縛られず、スキーヤーとして次のステージをイメージした。ソチオリンピック後、競技から離れ、ビッグマウンテンスキーへの本格的な挑戦をスタート。自らの資金、プロデュースで映像作品『Akira’s Project』を製作するなど、独自の活動は幅広いジャンルのスキーヤーや子供たちへ強い刺激を与えている。また、東北大震災復興支援団体“NPO Skiers Help Foundation”の設立、全日本スキー連盟アルペン国内強化ヘッドコーチなど活動の場は多岐に渡る。
全ての佐々木の活動は、一貫してスキーと人への愛で溢れている。スキーを通して「人間力の向上」を養い、実践する真の“スキー人”の発信は今後も見逃せない。
CLOSE

アンバサダー
プロスノーボーダー
(スノーボードクロス)
プロスノーボーダー
(スノーボードクロス)
高原 宜希〔Yoshiki Takahara〕

アンバサダー
プロスノーボーダー(スノーボードクロス)
プロスノーボーダー(スノーボードクロス)
高原 宜希〔Yoshiki Takahara〕
小学5年生で空手の福井県チャンピオンに輝き、中学校時代には野球部でキャプテンも務めるなど高い身体能力を誇り、スノーボードは5歳で始めた。2015年にJSBAアマチュアランキングで1位に輝き、同年に国内プロ資格を取得。国内プロデビュー戦でも優勝し、一躍注目選手に。SAJナショナルチーム内でも順調に成長を遂げ、2017-2018シーズンでは弱冠19歳でシニアW杯デビューを迎える予定だったものの、直前で怪我。しかし、再起をかけた2018年全日本選手権で見事初優勝を果たし、国内最高峰の実力者であることを証明した。そして2019年にはドイツでのW杯で日本人史上最高の4位に食い込み、一躍注目選手に躍り出た。2022年北京オリンピックにスノーボードクロス日本代表として出場。
CLOSE

アンバサダー
国立研究開発法人 防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター センター長
国立研究開発法人 防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター センター長
中村 一樹〔Kazuki Nakamura〕

アンバサダー
国立研究開発法人 防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター センター長
国立研究開発法人 防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター センター長
中村 一樹〔Kazuki Nakamura〕
- 1995年 日本気象協会 北海道本部勤務
- 2000年 同 北海道本部水文調査課長代理
- 2003年 同 北海道支社応用気象課長
- 2006年 同 北海道支社気象情報課長
- 2009年 同 北海道支社情報事業課課長
- 2009年 北海道大学大学院地球環境科学研究院 環境教育研究交流推進室 GCOE上級コーディネーター
- 2013年 防災科学技術研究所 雪氷防災研究センター新庄雪氷環境実験所
- 2016年 同 気象災害軽減イノベーションセンター センター長補佐・研究推進室長(兼)
- 2020年 同 イノベーション共創本部 共創推進室長(兼)
- 2022年 同 雪氷防災研究部門 部門長(雪氷防災研究センター センター長)
現在、日本雪工学会理事、中越防災安全推進機構理事、長岡市防災会議委員などを務める。
CLOSE

アンバサダー
プロスキーヤー
(フリースタイルモーグル)
プロスキーヤー
(フリースタイルモーグル)
堀島 行真〔Ikuma Horishima〕

アンバサダー
プロスキーヤー(フリースタイルモーグル)
プロスキーヤー(フリースタイルモーグル)
堀島 行真〔Ikuma Horishima〕
両親の影響で1歳でスキーを始める。小学4年時よりスキーの楽しさを常に感じながら本格的にモーグル競技に取り組む。中学3年の夏には全日本ウォータージャンプ選手権でビッグエアーで見事優勝を果たす。高校入学後は世界で活躍。高校3年時にはFIS W杯開幕戦で3位入賞するなどこのシーズンではFIS公認のルーキーオブザイヤーに選ばれる。中京大学に進学し2年時の2017年、世界選手権に日本代表として出場。その大会ではシングル・デュアル共に金メダルを獲得。2018年平昌オリンピック出場。2022年北京オリンピックでは銅メダルを獲得。
CLOSE

アンバサダー
プロスノーボーダー
(スノーボードアルペン)
プロスノーボーダー
(スノーボードアルペン)
三木 つばき〔Tsubaki Miki〕

アンバサダー
プロスノーボーダー(スノーボードアルペン)
プロスノーボーダー(スノーボードアルペン)
三木 つばき〔Tsubaki Miki〕
元JSBAテクニカル選手権優勝者の父親の影響で4歳からスノーボードを始め、小学4年生にはJSBA全日本選手権一般の部で優勝。史上最年少12歳でアルペンスノーボーダーのプロ選手となる。 プロ1年目、PSA ASIAプロランキングで3位となり、ルーキーオブザイヤー賞を受賞。プロ2年目(13歳)には、PSA ASIAプロランキング年間優勝を果たし、Best Rider of the year 受賞。海外でのジュニアレースにも出場し、5戦すべて優勝。 14歳でSAJナショナルチーム強化指定ユースに選抜。そして、ヨーロッパ各国を転戦するアルペ・アドリアシリーズ 2017-18(15歳以下女子の部)で、シリーズチャンピオンを果たす。 2019年1月、史上最年少(15歳)で日本代表(SNOW JAPAN)に選出され、スノーボード・ワールドカップに初出場。また、全日本選手権も史上最年少優勝を成し遂げる。さらに世界ジュニア選手権PSL(回転)種目で準優勝を獲得。 2021-2022シーズンは、FISランキング総合4位(女子アジア人トップ)まで昇りつめ、ワールドカップでは、初優勝を記録。世界ジュニア選手権ではPGS(大回転)、PS(回転)共に優勝。 2022年2月の北京冬季オリンピックではSNO
W JAPAN(スノーボードアルペン)日本代表として出場する他、ワールドカップでも初優勝を果たす。
CLOSE

アンバサダー
岩手大学 教授 博士(芸術学)
岩手大学 教授 博士(芸術学)
本村 健太〔Kenta Motomura〕

アンバサダー
岩手大学 教授 博士(芸術学)
岩手大学 教授 博士(芸術学)
本村 健太〔Kenta Motomura〕
- 1996年 岩手大学 教育学部 講師
- 2000年 ベルリン自由大学(ドイツ) 文部省在外研究員
- 2009年 岩手大学 教育学部 教授
- 2016年 岩手大学 人文社会科学部 教授
1968年生まれ。
芸術教育・総合芸術・「芸術と技術の融合」などをテーマに、近代デザインの基礎を築いたバウハウスの研究を行ってきた。また、この理論研究に並行して、基礎造形(ベーシックデザイン)から映像・アニメーションまで多岐に渡る表現を追求してきた。バウハウスの理論研究で学んだ時代精神と実験的精神を糧にして、スペキュラティブ(思弁的)なデザインやデザイン思考(デザインシンキング)によって、地域社会のよりよい未来を思い描くことを試みている。
雪への思い:
九州の熊本出身の私は、子どもの頃に雪に恵まれず、年に二、三回の積雪しかなかったように記憶しています。積もっても5センチいくかいかないくらいの状況でした。それでも雪が積もった朝には、いち早く登校して仲間たちと雪だるまを作っていました。校庭の土の上にちょっとだけしか積もっていない雪をなんとか集めて作るのです。壊れてはまた転がして、これを繰り返して小さかった雪だるまも徐々に大きくなっていくのを楽しみました。しかし、最後にはイメージしていた雪だるまとはまったく異なるものができあがりました。その雪だるまは、真っ白ではなく、白と土色のマダラ模様、泥だらけで汚かったのです。そうして、私は真っ白で大量の雪への憧れをもつようになりました。
運良く東北の岩手に移住した私は、この地の冬が大好きです。岩手の寒い冬が夏よりも好きなのです。自宅周辺の雪かきでさえ、真っ白な雪と格闘できるので私は大好きです。この身の引き締まるような真っ白な世界が毎年ちゃんとやってきてくれるのを私は切に願っています。
CLOSE
芸術教育・総合芸術・「芸術と技術の融合」などをテーマに、近代デザインの基礎を築いたバウハウスの研究を行ってきた。また、この理論研究に並行して、基礎造形(ベーシックデザイン)から映像・アニメーションまで多岐に渡る表現を追求してきた。バウハウスの理論研究で学んだ時代精神と実験的精神を糧にして、スペキュラティブ(思弁的)なデザインやデザイン思考(デザインシンキング)によって、地域社会のよりよい未来を思い描くことを試みている。
雪への思い:
九州の熊本出身の私は、子どもの頃に雪に恵まれず、年に二、三回の積雪しかなかったように記憶しています。積もっても5センチいくかいかないくらいの状況でした。それでも雪が積もった朝には、いち早く登校して仲間たちと雪だるまを作っていました。校庭の土の上にちょっとだけしか積もっていない雪をなんとか集めて作るのです。壊れてはまた転がして、これを繰り返して小さかった雪だるまも徐々に大きくなっていくのを楽しみました。しかし、最後にはイメージしていた雪だるまとはまったく異なるものができあがりました。その雪だるまは、真っ白ではなく、白と土色のマダラ模様、泥だらけで汚かったのです。そうして、私は真っ白で大量の雪への憧れをもつようになりました。
運良く東北の岩手に移住した私は、この地の冬が大好きです。岩手の寒い冬が夏よりも好きなのです。自宅周辺の雪かきでさえ、真っ白な雪と格闘できるので私は大好きです。この身の引き締まるような真っ白な世界が毎年ちゃんとやってきてくれるのを私は切に願っています。
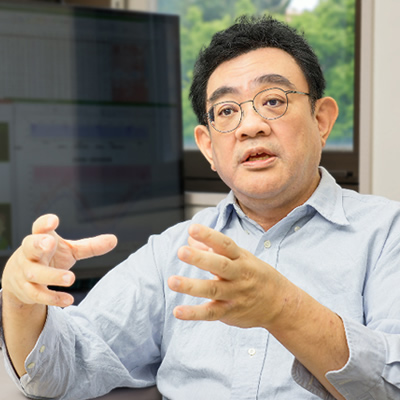
アンバサダー
北海道大学大学院 地球環境科学研究院 統合環境科学部門 実践・地球環境科学分野 教授
北海道大学大学院 地球環境科学研究院 統合環境科学部門 実践・地球環境科学分野 教授
山中 康裕〔Yasuhiro Yamanaka〕
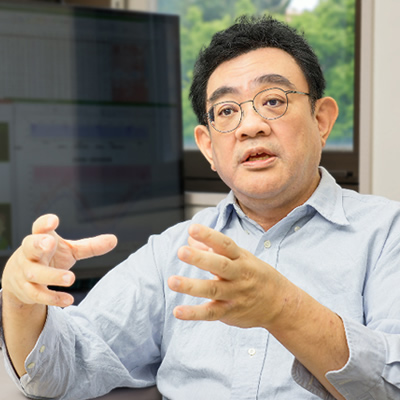
アンバサダー
北海道大学大学院 地球環境科学研究院 統合環境科学部門 実践・地球環境科学分野 教授
北海道大学大学院 地球環境科学研究院 統合環境科学部門 実践・地球環境科学分野 教授
山中 康裕〔Yasuhiro Yamanaka〕
- 1991年10月 - 1998年03月 東京大学気候システム研究センター 海洋モデリング部門 助手
- 1997年04月 - 1998年03月 米国プリンストン大学大気海洋プログラム Visiting Researcher(兼)
- 1998年04月 - 2010年09月 北海道大学大学院地球環境科学研究科/研究院 助教授/准教授
- 1998年05月 – 2003年06月 地球フロンティア研究システム地球温暖化予測領域炭素循環グループ グループリーダー(兼)
- 2007年11月 - 2008年02月 英国イーストアングリア大学環境科学部 Visiting fellow(兼)
- 2010年10月 - 現在 北海道大学大学院地球環境科学研究院 教授
気象庁 気候問題懇談会検討部会委員、文部科学省・気象庁・環境省 気候変動の観測・予測・影響評価に関する統合レポート「日本の気候変動とその影響」専門家委員会委員などを歴任
現在、札幌市環境審議会会長、北海道ゼロカーボン協議会座長、北海道環境審議会地球温暖化対策部会長、2050年北海道温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた懇話会座長、北海道環境教育等推進懇話会座長、国連大学認定RCE北海道道央圏副代表を務める。
CLOSE
現在、札幌市環境審議会会長、北海道ゼロカーボン協議会座長、北海道環境審議会地球温暖化対策部会長、2050年北海道温室効果ガス排出量実質ゼロに向けた懇話会座長、北海道環境教育等推進懇話会座長、国連大学認定RCE北海道道央圏副代表を務める。